深い蒼を湛えた水槽の中、氷のように冷たい水がヒールの肌を締めつける。
彼女は必死にガラスを叩くが、分厚い壁がその手を虚しく跳ね返す。背後には無機質な装置が並び、白衣の研究者が冷静に端末を操作していた。
「──準備完了。生体エネルギーの測定を開始します。」
モニターの数値が跳ね上がり、緑のレーザーが水中を奔る。
水圧がじわりと変化し、ヒールは苦悶の息を漏らすが、その瞳はなおも強く輝いていた。
「なにを——!」
「静かに。これからが本番です。」
水槽の底から、うねるように伸びてくるのは植物のような触手。
艶めいた表皮から滴る液体をまといながら、一本がヒールの太ももへと絡みつこうとしていた──。

手始めに、棘のある触手がヒールの喉奥深くへとねじ込まれる。
「おぶっ……ボゴッ……!」
水中での呼吸すらままならぬ状況で、気道までも塞がれる徹底ぶり。
それほどの制圧を加えなければ、彼女の異常なまでに鍛え上げられた肉体は、すぐさま形勢を逆転してしまう。
カンフースタイルのヒールにとって、この拘束は“必要最低限”だ。
観客も、あっけない幕切れなど求めていない。だからこそ、慎重に、そして丹念に“調理”する必要がある。

深く、冷たく、青い水槽の中――
囚われたヒールは、ただ静かに沈んでいた。
耳へ、鼻腔へ、口内へと忍び込む異形の感触が、境界を曖昧にする。
へそから股間へと滑る触手は、容赦なく彼女の輪郭を奪っていった。
眼窩の奥でうごめく異物。
揺れる泡の向こうで、誇りさえも少しずつ濁ってゆく。
「ゴボ…ボゴボッ……」
声なき叫びは、水に吸い込まれ、消えていく。
ひと蹴り、またひと蹴り──それはもはや誇りというより、反射的な痙攣にすぎなかった。
水槽の壁が微かに揺れ、泡が優雅に舞うたび、機械は冷ややかに進捗を読み上げる。
誰も来ない。何も終わらない。
光の届かぬ水底に残されたのは、もはや痛みさえ超えた、絶望の中でゆっくり崩れてゆく誇りの残骸だった。

開かれたすべての隙間を逃さず、ねっとりと這い寄る触手。
それは慈悲も戸惑いもなく、柔らかな彼女の奥深くへと滑り込んでゆく。
その体内で、何が、どんなふうに、蠢いているのか──想像すらためらわれる。

水槽の中、彼女は無表情のまま触手に貫かれる。
耳奥へ、へそ奥へ、口腔へ──粘液を滴らせながら、触手はじわじわと脳と内臓を目指して侵入していく。
ぐちゅっ……!脳に到達した瞬間、全身が跳ねた。
「ぶぼっ、ゴボゴボ……っ♡ い゛っ……ひ、ぎぃぃっ……!!」
泡混じりの悲鳴を漏らし、白目を剥いたまま身体がビクビクと痙攣する。
快楽と激痛が引き裂き、意識は崩壊の淵へ沈んでいった。

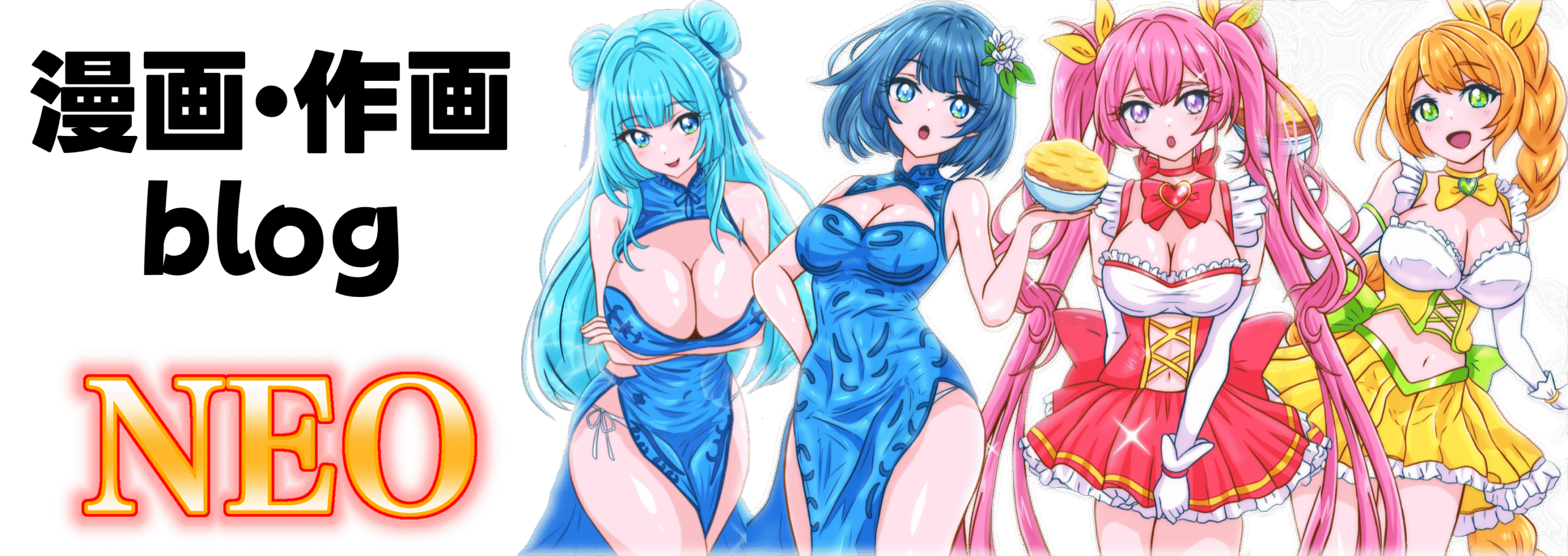



コメント